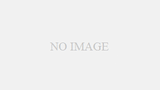人間さながらの動きで関節を使いバック転する宇樹科技(ユニツリー・ロボティクス)のロボット(24年8月、北京) 世界で人工知能(AI)を持つヒト型ロボットの開発競争が加速している。中でも過熱しているのが中国だ。「2025年に量産を始め、27年に世界トップとなる」。政府が23年秋に掲げた野心的な目標を機に投資に火がついた。 「ロボットがヒト型である必要があるのか」。翌24年夏、北京で開かれた世界ロボット大会で新興企業、宇樹科技の技術者にこう聞いたことがある。会場の様子が前年とは一変し、有象無象のヒト型であふれかえっていたためだ。 産業ロボット大国の日本はヒト型の研究でも先行したが、介護や医療など実際の社会実装では「車輪にアーム」といった実用型を優先した。そんな日本的観点から「現実的には用途別のシンプルな構造が便利では」と聞くと、中国の技術者はこう答えた。「人間に用途はないですよね。どこでも何でもできる。ロボットも同じです」 北京で開かれた「世界ロボット大会」ではヒト型ロボットが大量に出展された(24年8月、北京) ヒト型ロボット=マンパワーそのもの おそらく中国が一足飛びにめざすロボットという存在は車やスマホのような「人間を助ける便利な道具」にとどまらない。マンパワーそのものだ。そしてマンパワーは国勢であり国力そのものでもある。中国が量産と低価格化に突き進むことで世界の労働力におけるヒト型ロボットの浸透速度は大幅に早まるだろう。それは「中国が各国の国勢を直接左右できる時代」という危険な側面も併せ持つ。 中国のロボット戦略は中国の別の経済覇権とも密接にリンクしている。政府が「25年量産目標」を公表した23年11月2日の翌日、李強(リー・チャン)首相は国務院(政府)常務会議でこう訴えた。「レアアースは戦略的な鉱物資源だ。探査、開発、利用、規則的管理を政府が一括でとりまとめる」 同11月7日、政府はレアアース73項目に輸出報告義務を課し、12月21日にはレアアース磁石の製造技術の輸出規制を発表した。 なぜ中国はヒト型ロボットで突如、世界の先頭に躍り出たのか。その秘密はロボットの関節に使うレアアース磁石の技術力にある。 ロボットにおいて自動車のエンジンにあたる基幹部品は関節を制御するサーボモーターだ。サーボモーターの性能は、ネオジムなどを使ったレアアース磁石が左右する。そのレアアース磁石はかつては日本が優勢を誇ったが、今は世界シェアの8割を中国が握る。 米モルガン・スタンレーによるとヒト型ロボットの世界での普及台数は50年に10億台を超え、米中や高所得国の労働力の3〜4割を代替する。一方、ロボット1台は2〜4キログラムのネオジム磁石を使い、0.6〜1.3キログラムのネオジムプラセオジム合金を必要とする。 ロボット普及で強まる中国のレアアース覇権 この推計と英ウッド・マッケンジーの鉱物関連の需給予測を合わせると、ロボットの急速な普及を受けて同合金は37年から供給不足に転じ、不足量は46年に47%に達する。中国のレアアース覇権は強まる一方だ。世界がこの状態のままロボットの労働に依存する社会に移行すれば、その先に待つのは「中国支配にますます逆らえないディストピア」となりかねない。 世界がこうした事態を回避するためには、レアアースの生産を拡大するか、消費を減らすしかないが、道のりは容易ではない。 米国や日本は新鉱山の開発を急ぐ方針だが、探査から生産までには15年以上かかるという。現状の規模感では追いつかないだろう。ネオジム磁石の代替技術は既にあるものの、高性能のネオジムを使わずに最先端のロボット開発に挑むのは、激しい開発競争の中で重い足かせとなるのは間違いない。 そんな状況下、日本政府もAIロボットの活用に向けて基本計画を策定する方針を打ち出した。ロボットの用途などが柱の方向だが、中国の覇権を阻止するシナリオがないままにただ普及をめざす政策は亡国の戦略となりかねない。 振り返れば日本は電気自動車や電池、造船など得意のはずの産業で何度も中国から苦汁を飲まされてきた。中国と比べた敗因の1つに日本の産業政策における国家戦略や中長期的視点の欠如がある。 「水素社会」はその代表例だ。日本が世界に先駆けて提唱した戦略だが、企業が事業化していた乗用車の普及策などが中心で、最重要の水素の調達は最初から輸入を選んだ。一方、中国は水素を石油に次ぐ次世代のエネルギー安全保障の一手ととらえ、気づけば世界トップの水素生産大国となった。 日本は中長期的視点で産業政策を 日本は原因の見えている「失敗の連鎖」からいつ脱却するのか。 まずはチャイナリスクに直面するロボット戦略を出直しの試金石とすべきだ。この局面で戦略の一丁目一番地はレアアース問題以外はありえない。「解決できねばヒト型の活用は最小限とする」。そんな究極の選択も視野に入れながら数十年先を見据え、国の資源や資金、人材の配置を設計し、AIやエネルギー、素材など点在するイノベーションをつなげていく。 こうした手法は計画経済や国家資本主義のようで本来、自由経済には似つかわしくないかもしれない。だが、今の自由主義社会は「圧倒的な産業競争力を持つ専制国家の台頭」という一種のバグに直面している。想定外の事態に対応したバージョンアップは必要だ。 一方、政治の現場では再配分や世代を巡る対立が深まり、20日の参議院選挙後も「決められない政治」が続く見通しだ。民主主義の議論は尽くしつつ、経済成長を巡る国家戦略は政治の混乱から切り離し、中長期的視点を確保する――。中国の脅威はそんな政治のバージョンアップをも促している。 【関連記事】 ・習氏の「備え」がトランプ氏押し切る 米国、対中関税115%下げ ・「SHEIN村」にみる中国製造業の憂鬱 利益なき繁忙 ニュースを深く読み解く「Deep Insight」一覧へ 「日経電子版 オピニオン」のX(旧Twitter)アカウントをチェック
なぜ中国はヒト型ロボットで突如、世界の先頭に躍り出たのか。その秘密はロボットの関節に使うレアアース磁石の技術力にある。
 未分類
未分類